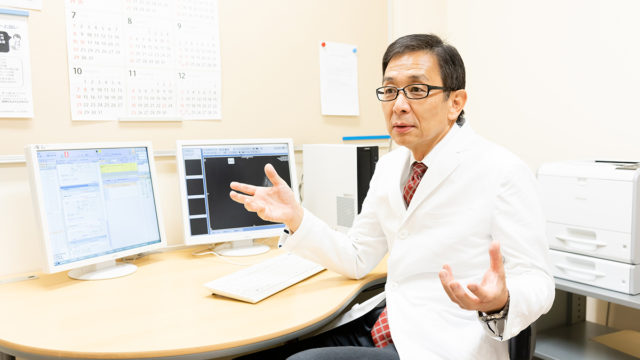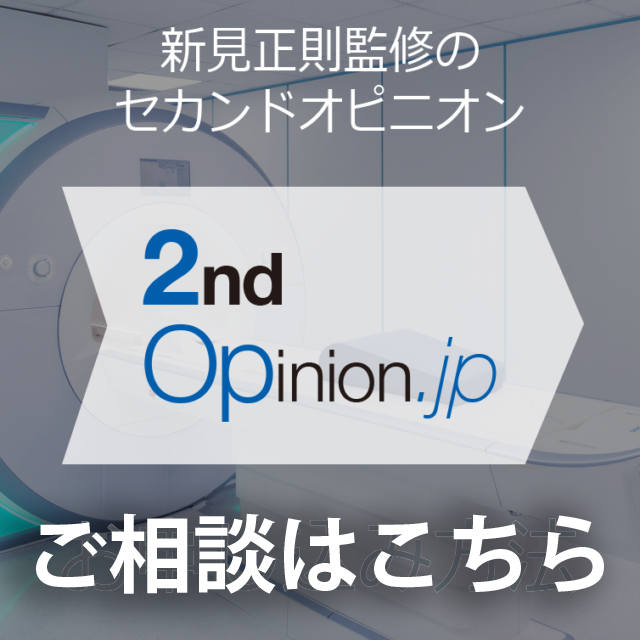医師に対する不信感はどこから生まれるか

セカンドオピニオンを患者さんが希望する根底には不安感があります。そこには医療の不完全性と不確実性があるからです。そんな状態でネットサーフィンをしても答えに辿り着かないのです。多くは根拠のない経験談のブログや、エビデンスのない医療情報を発信するメディアに翻弄されるのです。
●人はいろいろ
人は器械ではありません。DNAと言う4つの核酸が連続する遺伝情報からタンパク質が合成され、そしてそのタンパク質から体が形作られます。背や体つき、皮膚の色、血液型、声色、顔かたちなどなど千差万別です。そしてDNAがまったく同じ一卵性双生児でさえ、性格は違います。彼らが罹患する病気も同じではありません。一卵性双生児でさえ、異なるのですから、DNAが同じでない人の集団ではもっと違うはずです。
ですから、ある薬剤がある人には有効であるが、ある人にはあまり効かないということも起こりうるのです。医療ではレスポンダー(反応する人)とノンレスポンダー(反応しない人)とも呼ばれます。そんな違いが遺伝子レベルでも徐々に解析されています。遺伝子を調べてより有効な薬剤を決めようという試みです。しかし、これもまだまだ始まったばかりなのです。すると、レスポンダーかノンレスポンダーかわからない状態で治療を行うことになるのです。
副作用が少ないものであれば、効かなければ次を試そうという作戦が可能ですが、副作用が強烈であれば、最初から有効であって欲しいですね。そんな「人はいろいろ」といった当たり前の前提が医療を不正確で不確実にしているのです。そんな説明を十分にされないと、「効くと言うから治療してもらったのに、効かなかった」といった齟齬が生じます。また、医師の方も絶対に効くと断言できないので、そんな控えめな態度もある時は不信感を招いてしまいます。
●治療方法もいろいろ
治療方法も複数存在することが多いのです。そしてどの治療方法がもっとも優れているかの判断がまた難しいのです。僕は効果には5種類あると思っています。つまり推奨度が5段階あるということです。「絶対にこれ」、「ほぼこれ」、「これかな」、「ほぼやらない」、「絶対にやらない」の5種類です。
ある治療が本当に有効かを知ることは結構難しいのです。「○○を飲んでこれが治った」と患者さんが感じても、それは本当にその薬を飲んで治ったのか、たまたま時間経過で治ったのか、他の治療で実は快方に向かったのかの区別が付きません。
そんな疑問を解決する最善の方法が二重盲検臨床研究(RCT)と言います。医者も患者も知らない状態で臨床研究をするという意味です。有効成分を含む本当の薬剤(実薬といいます)と有効成分を含まないが実薬そっくりの薬剤(偽薬といいます)を用意します。
そして実薬と偽薬のどちらが投薬されたかを医者にも患者にも知らせずに、その効果を判定します。その判定が出揃ったあとに、実薬であったか偽薬であったかを確認し、実薬が明らかに偽薬よりも効果があることが最良の説得材料なのです。医療では最良のエビデンスがあると言われます。
▲絶対にこれ
出血が止まらなければ、出血を止める努力をするでしょう。そうしなければ失血して死亡します。また、以前は難治であった細菌感染症はペニシリンの登場で治る病気になりました。以前は不治の病であった結核はストレプトマイシンの登場で治癒する病気になりました。
このペニシリンやストレプトマイシンは実は二重盲検臨床研究をやっていません。ペニシリンの登場で細菌感染症が治り、ストレプトマイシンの登場で結核が治り、死亡者が明らかに減ったからです。つまり劇的に効く薬には二重盲検臨床研究は不要なのです。二重盲検臨床研究が不要なほど劇的に効く薬とも言えます。誰もがその効果を認めざるを得ないほど有効ということです。
▲ほぼこれ
確かに効いている気はするが劇的とまでは言えないという時は悩ましいのです。医者も患者も良くなると行った治療のお陰だと思いたくなるのです。患者さんの施された治療で治ったと信じたいのです。このような思い込みをプラセボ効果と言います。
そんな時にこそ二重盲検臨床研究が必要です。そんな二重盲検臨床研究で統計的な差をもって勝つと日本では保険適用の薬になります。二重盲検臨床研究で勝ち抜くのは本当に難しいのです。製薬メーカーは二重盲検臨床研究を勝ち抜いて新薬を開発しているのです。そして二重盲検臨床研究で勝てば堂々とエビデンスを獲得したと言えます。
▲これかな
これは臨床経験豊富な医師が効くと感じているが、二重盲検臨床研究がないものです。漢方薬も実は保険適用されていますが明らかな二重盲検臨床研究はありません。明らかなとは「一流英文論文」に採択されているかという視点です。
一流英文論文に載せるには相当なハードルを越える必要があるのです。しかし、一流英文論文には載っていないが、和文や一流とまでは言えない英文誌に二重盲検臨床研究があるものはある程度説得材料になります。また現在、二重盲検臨床研究を進行中のものも将来が楽しみです。
▲ほぼやらない
漢方薬を除いて保険適用西洋薬は二重盲検臨床研究を勝ち抜いています。一方でサプリメントは通常二重盲検臨床研究を行っていません。ですから「個人の感想です」と言った注釈が付くのです。しかし、副作用がほとんどなく、本人が使用して有効性を感じれば、それを否定する根拠もありません。
▲絶対にやらない
医療従事者が明らかに間違いと思うことです。
| 絶対にこれ | RCT不要 しなくても明白 |
| ほぼこれ | RCTで統計的に差がある |
| これかな | RCTで統計的な差はない |
| ほぼやらない | RCTを行う気がない |
| 絶対にやらない |
医療行為で「絶対にこれ」というのが実は多くはありません。ほとんどが「ほぼこれ」以下の治療なのです。つまりやっとRCTで統計的有意差が出る程度ということです。ですから、正しく医療を俯瞰している医者ほど「絶対に治る」と言えなくなるのです。そんな点も患者サイドからすれば医療不信の一因になります。
●病院、大学、医局
どの医療行為が本当に正しいかは現状では正確には判断できないのですが、将来正しい結論に収束していくのです。つまり歴史が証明するのです。そんな歴史が実は大切なのです。長い歴史をもっている医学部には智恵の集積があります。そして歴史ある医学部は関連病院を多数握っています。関連病院も大学医学部との友好的な関係がないと維持できません。
そして何が現状正しいかが判然としない以上、いろいろな意見が生じますが、あるグループではほぼほぼ同じ治療が行われるのです。そのグループの中心が大学医学部の医局制度です。医局制度の利点または欠点はいろいろとありますが、重要な役割を担っていることは間違いありません。
セカンドオピニオンを行う時に大切なことは、特に治療方針についてのセカンドオピニオンでは、医局が違う医師の意見を聞くことが大切です。同じ医局の医師は同じようなコメントをすることが多いからです。
●ハイコンテクストとローコンテクストの文化
日本はハイコンテクストの文化です。聞き手の能力を期待する傾向があります。以下のような特徴があります。
- 直接的表現よりも凝った描写を好む
- 曖昧な表現を好む
- 多くは話さない
- 論理的飛躍が許される
- 質疑応答の直接性を重視しない
アメリカは他民族、移民国家で典型的なローコンテクスト文化です。話し手の責任が重いのです。以下のような特徴があります。
- 直接的で解りやすい表現を好む
- 言語に対して高い価値と積極的な姿勢を示す
- 単純でシンプルな理論を好む
- 明示的な表現を好む
- 寡黙であることを評価しない
- 論理的飛躍を好まない
- 質疑応答では直接的に答える
簡単に言うと「古池や蛙飛びこむ水の音」とか「柿食えば鐘が鳴るなり法隆寺」という短い文章から、ハイコンテクストの文化では、情景が浮かび上がるということです。空気が読めるということにも通じます。行間が読めるという意味合いもあります。そんな文化では、お互いが共通したハイコンテクストであれば問題ありませんが、そこにズレが生じると不安や不信に繋がるのです。
ハイコンテクスト文化では、治療の説明は、以前わが国で行われていたように「○○という病気ですから、△△という治療をします。」でほぼお話しは終了出来たのです。上手く行けばお互いにそれを喜び合って、結果が悪ければ、「残念だが致し方ない」と思えたのです。
ところが、そのハイコンテクスト文化の日本に、インフォームドコンセントというローコンテクスト文化が入って来ました。「詳細に説明して了解をとれ」という作戦です。雰囲気で語り合ったり、行間を読んだりしないとうことです。すべてを説明しろという文化です。そして医療者と患者という情報量とその理解に雲泥の差がある状態でインフォームドコンセントを行っても通常は患者サイドが理解不能になります。そんな文化的な不一致も医療不信の一因になっています。
●医療は不完全で不確実
医療は現状では不完全な部分が多く、不確実性を拭えません。将来、どんな医療が正しいかは徐々に判明します。しかし、医療サイドは今治療を行わなければならないのです。ですから、得られる知識を総動員して、現状での最善の策を提示するのです。医療は試行錯誤を繰り返して進歩します。
二重盲検臨床研究が最良のエビデンスといっても、多くても10万人規模の臨床研究です。通常は1000人規模が多いのです。100人規模の研究も少なくありません。つまり全体を代表しているとも限らないのです。ですから、二重盲検臨床研究も複数ある方が説得力は高くなります。相反する結果が出ることもあるからです。
すると、現在施されている医療は、今までに登場した臨床研究や、医療サイドの経験知の蓄積からの精一杯の結論なのです。そんな不完全で不確実な医療は、実際の臨床で、つまり人体実験を通じて再確認され、訂正され、そして進歩しているのです。ある世代の膨大な医療情報を解析して、そしていろいろな因子の関与を観察すると相関が得られます。そんなビッグデータ解析を行うと、理屈抜きで結論が導き出せてしまうのです。そんなビッグデータ解析で得られる健康や医療情報を次世代に残す責務も我々の世代は担っているのです。
●現場主義になっていない
医療では残念ながらビジネスでは当たり前の現場主義になっていません。つまり患者さん(顧客)は、「当然に長生きを求めている」と決めつけています。永くセカンドオピニオンをやっていて、超現場主義になっている僕には患者さんの気持ちがわかるのです。辛い思いをして数ヶ月長生きするぐらいなら、辛い思いをしないで潔く旅立ちたいという願いです。そんな願いをなかなか医療サイドは聴けません。
特に若い医師にはその立場を理解すること自体が難題です。実際に僕も若い頃は「潔く旅立とう」とは決して言えませんでした。母が潔く旅立って自信を持ってそう言えるようになったのです。ですから、命に関わる病気の相談は、ある程度経験を積んだ医師がいいでしょう。両親や配偶者を送ったことがある医師がいいと思っています。患者の幸福度も勘案した人工知能による人それぞれに対する医療情報の提供、それをここではセカンドオピニオン4.0の究極の形としています。
●次善の策を知らない医師達
医師として次善の策を知っていることは大切です。いろいろな選択肢を考えた上で最良の治療を選択したのか、またはガイドラインに書いてあるからその治療を選んだのかは大切です。選択した最善の治療と次善の治療の差を知っていることが重要なのです。
最善の治療と次善の治療に患者さんにとっての明らかな御利益の差があることが重要です。臨床研究で統計的に有意差がある薬が厚生労働省から認可されて実臨床で使用できます。ここでいう統計的有意差と患者さんにとっての御利益に解離があることが問題なのです。
統計的有意差とは、例えば全例で3ヶ月の延命が得られれば明らかに差があるのです。しかし、その3ヶ月を得るために、副作用で苦しむ期間が3ヶ月以上あれば、患者さんにとっての御利益はどれほどのものなのでしょうか。主治医がこんな視点を持っているかどうかが重要です。